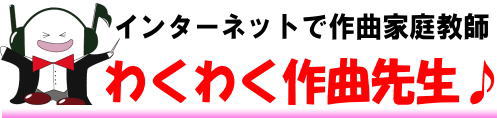今回は「半音上がる転調」について説明します。
ここまでいろんな作曲テクニックを紹介してきましたが、たくさん紹介してきたので。
忘れていることがあれば、作曲編曲のやり方87の法則の目次に戻って復習してくださいね。
半音上がる転調の使い方
さて、今回はちょっとウォーミングアップとして、
最も簡単な転調方法をご紹介します。
よく、曲の後半部分で半音上がるパターンがありますよね。
これは前回(転調の種類を解説)紹介した
●一時的な転調
●本格的な転調
の「本格的な転調」にあたります。
半音上げ転調の作り方は、とてもシンプルです。
曲の流れがひと段落したところで、これまでのコード進行をそのまま半音上げて繰り返します。
例えば「C-Am-F-G」を3回繰り返して「Dm – G – C」で一段落した後、
半音上げの「C#-A#m-F#-G#」というコード進行に転調します。
半音上げ転調の使いどころと注意点
「あっ、転調した!!」と分かるような、急激な転調は、
どのような場面で使えば効果的でしょうか?
よくあるパターンは、
●後半繰り返しになる場面で転調
●Aメロ、Bメロなどブロックごとに転調
●間奏だけ転調
など、単純な繰り返しの多い時や、型にはまった(次が予想できる)場面に使われることが多いです。
その理由は、リスナーが「次もこう来るだろうな」と予想する流れを、
良い意味で裏切り、新鮮さを与えるからですね。
そして、keyを半音上げると、ヴォーカルのテンション(気合い)も上がるので、
曲が盛り上がります。
そのため、ラストのサビで半音上げるのも効果的な使い方です。
ただし、この方法はヴォーカルの音域を考えて、無理のない範囲で使わないと
ヴォーカルに負担がかかってしまい、逆効果になってしまう場合もあるので、
注意して使いましょう。
次回も転調の続きを紹介します。
次の講座_第23回「セカンダリードミナント」を読む
前回の講座_第21回「転調の種類と方法」を読む
「作曲編曲のやり方87の法則 」もくじへ戻る
初心者からのオンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る