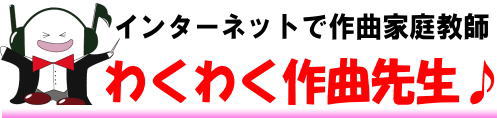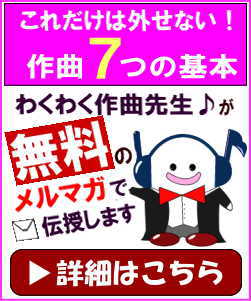DTMで曲を作るとき、特にミキシング段階では、
エフェクトをうまく使うことで、楽曲のクオリティが格段に上がります。
エフェクトにはさまざまな種類がありますが、
初心者のうちは、何をどう使えばいいのか分からないことも多いですよね。
そこで今回は、「DTMでよく使うエフェクトの種類」とその使い方について、初心者にも分かりやすく解説していきます。

また、エフェクトの設定のコツやかけすぎ防止のポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください!
そもそもエフェクトとは何?
エフェクトとは、音を加工するためのツールのことです。
たとえば風呂場で歌うと、声がよく響くような現象もエフェクトの一種ですね。
DTMでは、さまざまなエフェクトを活用することで、
音に奥行きを加えたり、迫力を出したり、クリアにしたりできます。
では、DTMでよく使われるエフェクトを見ていきましょう!
DTMエフェクトの種類と使い方
エフェクトにはさまざまな種類がありますが、
大きく分けると以下の6つに分類できます。
1. 空間系エフェクト(リバーブ・ディレイ)
空間系エフェクトは、音に広がりや奥行きを加えるために使います。
- リバーブ(Reverb):残響音を付加し、音に深みや広がりを与えるエフェクト。
ボーカルやストリングス、ピアノなどに使うと、自然な響きを加えられます。 - ディレイ(Delay):音を遅らせて繰り返し鳴らすエフェクト。
ギターソロやボーカルに使うと、幻想的な雰囲気を作れます。
また、すごく時間の短いディレイを使うことで、音に厚みを持たせることもできます。
2. ダイナミクス系エフェクト(コンプレッサー・EQ)
ダイナミクス系エフェクトは、音そのものを加工して、
バランスを整えたり、聴こえ方を調整したりするために使います。
- コンプレッサー(Compressor):音を圧縮して音圧を上げたり、アタック感を強調できるエフェクト。
音を圧縮して音圧を出すことが出来るので、たとえばドラムに使うと、迫力のあるドラムサウンドを作ることが出来ます。
音量の変化が激しい楽器(またはヴォーカル)に使って、音量の差を抑えるような使い方もできます。 - EQ(イコライザー):特定の周波数帯の音量を上げたり下げたりして、音質を調整するエフェクト。
たとえば、ボーカルのこもった感じを解消したり、ベースの輪郭をはっきりさせたり、
音がかぶっている楽器同士の周波数帯をずらして聞こえやすくできます。
3. 歪み系エフェクト(ディストーション・オーバードライブ)
歪み系エフェクトは、音を意図的に歪ませることで、迫力や荒々しさを加えます。
- ディストーション(Distortion):激しく歪んだサウンドを作るエフェクト。主にロックやメタルのギターに使用。
- オーバードライブ(Overdrive):ディストーションよりもマイルドな歪みを作るエフェクト。
ブルースやポップスのギターに適しています。
ギター以外にも、ドラムやベースに軽くかけることで、音に存在感を持たせることができます。
4. モジュレーション系エフェクト(コーラス・フランジャー・フェイザー)
モジュレーション系エフェクトは、音を揺らしたり厚みを加えたりする効果があります。
派手に使うと独特な雰囲気を作れますが、過剰にかけると音が不明瞭になりやすいので注意が必要です。
- コーラス(Chorus):ディレイ音に揺れを加え、複数の楽器で鳴らしているような広がりのある効果を作るエフェクト。
リバーブが全体的に広がるのに対し、コーラスは左右に広がります。そして、「揺れ」が加わります。
ストリングスやパッドのような、広がりが欲しい楽器に適しています。 - フランジャー(Flanger):基本的にはコーラスと同じですが、金属的な“うねり”を生み出すエフェクト。
ギターやドラムに使うと、おもしろい空間的な変化が生まれます。 - フェイザー(Phaser):原音に、位相をずらした音をミックスし、このズレに「揺れ」を加えたエフェクト。
フランジャーよりも自然な揺れになります。エレクトリックピアノやギターによく使われます。
5. フィルター系エフェクト(ワウ・ローパス・ハイパス)
フィルター系エフェクトは、特定の周波数帯域をカットしたり強調したりすることで音色を変化させます。
ミックスの中で不要な音域を整理するのにも役立ちます。
- ワウ(Wah):ギターやシンセで「ワウワウ」と鳴らす効果を作るエフェクト。
- ローパスフィルター(LPF):高音域をカットして低音を強調するエフェクト。EDMやヒップホップのサウンドデザインによく使われます。
- ハイパスフィルター(HPF):低音域をカットしてクリアな音を作るエフェクト。ボーカルミックスやドラムの処理によく使います。
6. ピッチ系エフェクト(ピッチシフター・オートチューン)
ピッチ系エフェクトは、エフェクトに分類できるかどうか微妙なところですが、
音程を変化させるために使うツールです。
- ピッチシフター(Pitch Shifter):音程を上下させてハーモニーを作ることができます。
ギターやボーカルに使うと、厚みのあるサウンドが作れます。 - オートチューン(Auto-Tune):ボーカルのピッチ補正を自動で行います。
あえて大げさにかけることで、「ケロケロボイス」と呼ばれるような、EDMやヒップホップのボーカル加工にもよく使われます。
初心者向けのエフェクト設定のコツ & かけすぎ防止策
エフェクトは便利ですが、かけすぎると逆に音が濁ったり、不自然になったりします。
ここでは、エフェクトを自然に使うためのコツを紹介します。
- かけすぎに注意する
リバーブやディレイはかけすぎてしまうことが多いので、少しずつ調整しながら使いましょう。
ヘッドホンやスピーカーなど、いろんな環境でチェックすると、かけすぎに気が付きやすくなります。
コンプレッサーは「音圧を上げすぎない」ように注意しましょう。
音圧を上げると迫力が出ますが、やりすぎると奥行きが無くなり、平坦な音になってしまいます。 - 音を確認しながら調整する
ミックス全体で聴きながらバランスを取りましょう。
最初は楽器単体でエフェクト調整しても良いのですが、ある程度調整した後は、他の楽器とも一緒に鳴らして確認しましょう。 - プリセットを活用する
各エフェクトには「プリセット」があるので、初心者はこれを活用するのも一つの方法です。
プリセットの状態から、少しずつパラメーターを変更しながら調整すると使いやすいですよ。
DTMエフェクトの順番と適用のコツ
エフェクトをかける順番も重要です。順番によって音が変わります。
基本的な順番としては、
- EQ(不要な帯域をカット)
- コンプレッサー(音量を整える)
- 空間系(リバーブ・ディレイで奥行きをつける)
この流れを意識すると、クリアでまとまりのあるミックスになります。
また、モジュレーション系やフィルター系は、楽曲の雰囲気作りに応じて追加しましょう。
まとめ:DTMエフェクトを使いこなして楽曲をレベルアップしよう!
以上のように、いろんなエフェクトが有りますよね。
今回は、DTМでよく使われるエフェクトの種類を紹介しましたが、
最初は基本の「リバーブ・コンプレッサー・EQ」から始めて、
徐々に他のエフェクトにもチャレンジしてみてくださいね(^◇^)ノ