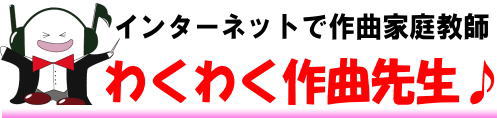今回はちょっと気分転換。
理論から離れて「作曲の感覚」についてお話しましょう。
このページ読者の中には、すでに作曲ができる方もいると思いますが、
通常、曲を作る時ってどのような手順で作ると思いますか?
一般的に思われているのは、
歌詞を書いて、メロディを付けて、アレンジという手順ではないでしょうか?
作曲手順の種類
作曲だけで考えると、
1,いいメロディがうかぶ
2,メロディにコードをつける
3,アレンジ
という手順を想像すると思います。
この手順は作曲家によりさまざまです。
僕の場合は、歌詞を先に頂かない限りは、
これと逆の順序で作っていきます。
1,頭の中で曲全体のイメージを固める
2,リズム(ドラムなど)を作る
3,作ったリズムに合わせて、コード進行を決めていく
4,メロディを考えながら、コードやリズムを微調整
5,装飾的なアレンジをして仕上げ
6,作詞
という流れが多いですね。
先に歌詞を頂いた場合は
また順序が変わります。
1,頭の中で、曲全体のイメージを固める
2,歌詞を見ながら、メロディとコードを同時に決めていく
3,アレンジをして仕上げ
これは一般的な順序に近いですね。
これらの方法はあくまでも僕のやり方であって、
やはり作曲家により異なります。
自分に最適の方法を見つけだしてくださいね。
作曲している時の感覚
曲を考えているときの感覚としては2通りあります。
1,理論優先
2,感覚優先
1,は理論を頭の片隅に置きつつ、キーボードで探りながら計算して作っていくやり方です。
2,はキーボードを自由に弾いてみたり、ぼーっとして何かうかんでくるのを待ったりします。
どちらが良いというわけではありませんが、
曲調が全然違ってきます。
僕の場合、1は玄人向けのシブイ曲、2は親しみやすい曲になります(人により変わると思いますが)。
ちなみに、僕がプロデュースしてダンスユニット「4th-signal」は1の方法,
会社やイベント用に提供している曲は2の方法で作ることが多いです。
次の講座_第87回「作曲したオリジナル作品の発表方法」を読む
前回の講座_第85回「DTMでのディストーションエフェクトの使い方」を読む
「作曲編曲のやり方87の法則 」もくじへ戻る
初心者からのオンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る