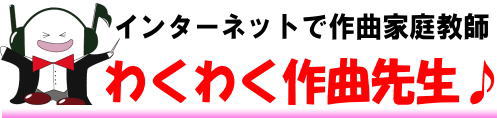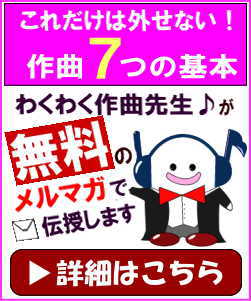今回は「DTMのインターフェイス」について、最新情報を交えながら紹介していきます。
DTMを楽しむためには、パソコンと外部機器を接続する必要があります。
その仲介役となるのが「インターフェース」です。
インターフェースには大きく分けて、
「MIDIインターフェース」と「オーディオインターフェース」の2種類があります。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
MIDIインターフェース
MIDIインターフェースとは、外部MIDI機器とパソコンをつなぎ、「MIDI信号」をやりとりするための装置です。

例えば、MIDIキーボード、電子ドラム、フィジカルコントローラーなどの
MIDI対応機器を接続する際に使います。
ですが最近では、ほとんどのMIDI機器がUSB接続に対応しているため、
専用のMIDIインターフェースを購入する必要はほとんどありません。
USB端子が付いている機器なら、直接パソコンに接続できることが多いです。
ただ、複数のMIDI機器を同時に接続したい場合や、
より安定した通信が求められる場面では、専用のMIDIインターフェースが活躍します。
そのような用途で選ぶ場合は、接続可能なポート数を確認しておきましょう。
オーディオインターフェース
オーディオインターフェースとは、マイク、ギター、シンセサイザー、スピーカーなどの
パソコン外部にある機器とパソコンをつなぎ、
「(信号ではなく)実際に鳴る音」をやり取りするための装置です。
パソコン外部の「実際に鳴る音」をパソコン内のDAWに入力(録音)したり、
パソコン内部の「実際に鳴る音」を、スピーカーやヘッドホンから高音質で出力します。

次に、オーディオインターフェースを購入する際に
チェックしてほしいポイントを挙げてみます。
① 入出力数
マイクやギターなどを、同時に何本接続できるかを示します。
たとえば、ソロ演奏なら入力1つで十分ですが、
バンド演奏や複数人での録音には、入力数が多いものが必要です。
なお、鍵盤付きのシンセなど、ステレオで鳴る楽器を取り込むには、
入力は2つ必要です。
② サンプリングレートとビット
これは、どれだけ忠実に「原音に近い音」を再現できるかという数値です。
現在の標準は24ビット/96kHzですが、192kHz対応のモデルも増えています。
初心者の方は、まずは24ビット/96kHz対応モデルを選べば問題ありません。
③ 端子形状
接続機器に合わせて、必要な端子があるか確認しましょう。
標準的なXLR端子(3ピンのマイク用端子)やTRS端子(1ピンのギター用など)、
さらにデジタル接続(S/PDIFやADAT)に対応したものもあります。
④ その他の機能
最近のモデルには、ダイレクトモニタリング(遅延なしで音を聞ける機能)や
ループバック機能(配信や録音で便利)が搭載されています。
用途に合わせて選ぶと良いでしょう。
接続方法について
インターフェースとパソコンを接続する方法も確認しておきしょう。
・USB
現在、USB接続が最も一般的です。
USB 3.0やUSB-C対応モデルは、高速なデータ転送が可能で、
安定したパフォーマンスを提供します。
特にUSB-Cは、プラグの形状が小型で、リバーシブルな接続が可能なので、
最近の機器では主流となっています。
・Thunderbolt
Thunderbolt接続は、USBよりもさらに高速なデータ転送が可能で、
プロフェッショナルな用途に適しています。
特にMacユーザーにとっては、非常に相性の良い規格です。
・PCIe
デスクトップPCの内部に直接装着するタイプです。
高度な処理能力が求められるスタジオ環境では今でも使われていますが、
一般ユーザー向けとしては外付けタイプが主流です。
初心者にありがちな選択ミス
オーディオインターフェースを初めて購入する際に、
初心者がよくやってしまうミスがあります。
これらに当てはまらないように気を付けましょう。
・入出力数を過小評価してしまう
例えば、将来的に複数人での録音を計画している場合、
入出力数の少ないモデルを選ぶと、後悔する可能性があります。
・サンプリングレートやビット数を過剰に重視する
初心者が「最も高性能なもの」を選ぼうとすると、
不要な機能にお金をかけてしまうことがあります。
・接続方法を確認しない
自分のパソコンのポート(入出力端子)に対応していないインターフェースを購入してしまうミスも多いです
たとえば、パソコンにThunderboltの端子が無いのに
Thunderbolt接続のオーディオインターフェイスを購入してしまう場合ですね。
ただ、複数の接続方法が出来るインタフェイスも多いので、
もし間違って購入しても、あきらめずに確認してみましょう。
オーディオインターフェースの最新技術トレンド
オーディオインターフェースの世界でも、技術革新は進んでいます。
注目すべきトレンドをいくつか紹介します。
・AIノイズ除去
録音中の環境ノイズをリアルタイムで低減する機能が登場。
・Wi-Fi対応
ワイヤレスでの接続が可能なモデルも増えており、スタジオ内での配線を減らすことができます。
・USB-C普及
高速データ転送と汎用性を備えたUSB-Cポートが、多くの新モデルで採用されています。
トラブルシューティングの基本
トラブルが起こったときでも、基本的な対処法を知っておけば安心です。
いくつか紹介しますね。
1,音が出ない場合
・ケーブルの接続を再確認する
マイクや楽器からオーディオインターフェース、さらにパソコンまでのケーブルがしっかり接続されているか確認しましょう。
もし断線している場合は交換が必要です。
・デバイスが正しく認識されているか確認する
パソコンの設定で、オーディオインターフェースが正しく選択されているかチェックしましょう。
特にWindowsでは、デフォルトの再生デバイスが切り替わっている場合があります。
2,ノイズが入る場合
・接続ケーブルやインターフェースの位置を調整する
ケーブルが電源アダプターやモニタースピーカーの近くを通っていると、
ノイズの原因になることがあります。
・別のコンセントを使ってみる
同じ電源タップに複数の機器を接続するとノイズが発生しやすくなります。
別のコンセントを使うと解決することがあります。
3,音の遅延が大きい場合
・バッファサイズを調整する。
DTMソフトの「オーディオ設定」で、バッファサイズを小さくすると遅延が減少します。
ただし、あまり小さくしすぎるとノイズが発生する可能性があるので、最適な設定を見つけましょう。
・他のアプリケーションを終了する。
パソコンのCPU負荷が高いと遅延が大きくなります。
不要なアプリケーションを終了させ、CPUやメモリの能力をDTMソフトに集中させましょう。
4,フリーズする場合
・ドライバーの更新を確認する。
メーカーの公式サイトから最新のドライバーをダウンロードしてインストールしましょう。
・接続方式を変えてみる。
USBポートを変更する、あるいは他の規格(USB-CやThunderbolt)に対応したポートを試すことで、安定性が向上する場合があります。
以上のように、外部機器を使う場合はインターフェイスが必要です。
今回紹介したことも参考にしながら、
インターフェイスを使ってみてくださいね(^◇^)ノ
→音楽制作の知識大全「音楽レシピ(作り方)の図書館」のもくじへ戻る