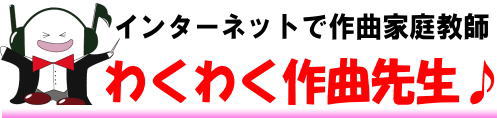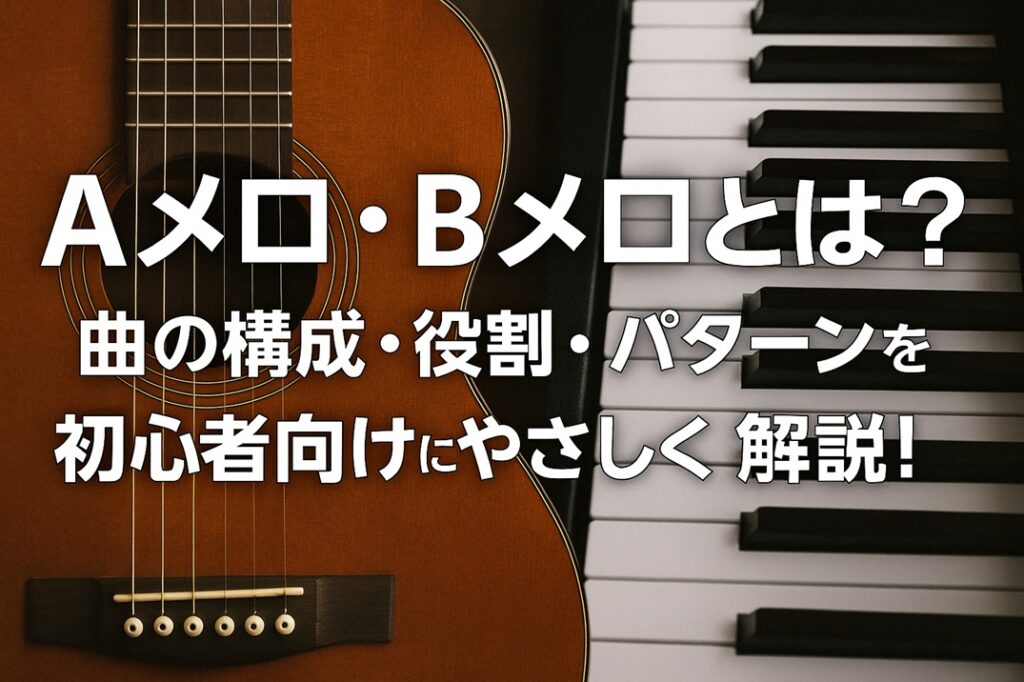「Aメロ」「Bメロ」ってよく聞くけど、実はよくわかっていない…という方も多いのではないでしょうか?
J-POPやアニソンなど、たくさんの楽曲で使われている「Aメロ・Bメロ・サビ」といった曲の構成。
でも、それぞれがどんな役割なのか、
どこからがAメロで、どこからがBメロなのか、ちょっと曖昧ですよね。
この記事では、プロ作曲コーチとして20年以上の経験を持つ僕が、
初心者の方にもわかりやすく「曲の構造」について解説していきます。
Aメロ・Bメロ・サビの違いはもちろん、実際の曲の構成パターンや
Cメロ・Dメロなどの応用まで紹介していくので、
曲を“聴く”のがもっと楽しくなり、曲を“作る”ヒントにもなるはずです♪
Aメロとは?Bメロとの違いや曲の基本構造をやさしく解説
「Aメロって何のこと?」
音楽を聴いていて、そんな疑問を持ったことはありませんか?
Aメロとは、J-POPなどの楽曲でよく使われる「曲構造の一部」を表す言葉で、曲の最初に登場するメロディのまとまり(ブロック)のことを指します。
そして、そのあとに続くのがBメロ。サビに向かって徐々に盛り上げていく役割を持つ部分です。
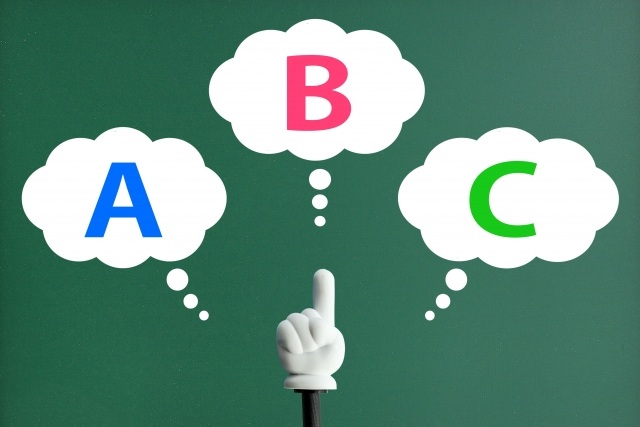
こうした「Aメロ」「Bメロ」「サビ」といった構成要素は、
曲の展開にメリハリをつけたり、感情をコントロールしたりするために、とても大切な要素なんですね。
Aメロとは?
Aメロは、多くの曲で歌の最初に登場する部分です。
メロディやリズムは比較的おだやかで、曲の世界観やストーリーを静かに伝え始めるような役割があります。
たとえば、映画のオープニングシーンのように、リスナーを作品の中へ引き込む「入口」となる部分ですね。
Bメロとは?
Bメロは、Aメロとサビ(Cメロ)の間に登場することが多く、
メロディやコード進行に変化を加えて、聴き手の感情を盛り上げていくパートです。
少しスピード感が出たり、リズムが変化したりして、
サビに向けて期待感を高めてくれる“つなぎ”の役割を果たします。
メロディがない曲でも使える考え方?
もちろん、インスト(歌のない曲)やBGMでも、
「Aパート」「Bパート」として、同じような構成を考えることができます。
この場合はメロディではなく、コード進行や展開の違いによってブロックを分けるイメージですね。
このように、「Aメロ」「Bメロ」はただのラベルではなく、曲全体の構成を支える大切な要素です。
次のセクションでは、Aメロ・Bメロ・サビの違いについて、
さらに詳しく見ていきましょう!
Aメロ・Bメロ・サビの違いと役割を比較!
「Aメロ」「Bメロ」「サビ」――
よく聞く言葉ですが、
それぞれどんな違いがあるのでしょうか?
この3つは、J-POPなど多くの楽曲でよく使われる、
曲の基本構造です。
それぞれが異なる役割を持っており、
うまく組み合わせることで、
聴きやすくて印象的な曲を作ることができます。
ここでは、「Aメロ」「Bメロ」「サビ」の、
それぞれの役割について見ていきましょう。

Aメロの役割:曲の世界観を静かにスタートさせる
Aメロは、曲の冒頭に登場する“導入パート”です。
リズムやメロディは控えめで、歌詞やメッセージをゆっくり伝えていくような部分が多いです。
この段階では、まだサビのような盛り上がりはなく、
“これからどんな物語が始まるのか?”という期待をつくるステージとも言えます。
Bメロの役割:サビへの「橋渡し」
Bメロは、Aメロのあとに登場し、サビへと感情を高めていくパートです。
コード進行やリズムに変化をつけたり、メロディの動きが大きくなることで、
ドラマ性や緊張感が生まれるのが特徴です。
Aメロで静かに始まった曲を、一気に盛り上げてサビに届けるための“ジャンプ台”のような存在ですね。
サビの役割:曲の“主役”であり、聴き手の心に残る場所
サビ(Cメロ)は、曲の主役です。
曲の中で最も印象に残る、感情が開放されるパートです。
タイトルに含まれる歌詞や、キャッチーなフレーズが登場することが多く、
リスナーが最も楽しみにしている部分でもあります。
Aメロ・Bメロがあるからこそ、サビの爆発力や感動がより際立つんですね。
このように、Aメロ・Bメロ・サビはそれぞれが役割を分担しながら、
曲に“起承転結”のようなストーリー性を与えているんです。
次の章では、これらのパートがどんな順番で組み合わされているのか、
見ていきましょう。
よくある曲構成をパターン別に紹介【特にJ-POPでよく使われる形】
Aメロ・Bメロ・サビの違いがわかってきたら、
次は、これらのパートがどのように組み合わされて、
曲が展開していくのかを見てみましょう。
J-POPをはじめとする多くの楽曲では、ある程度定番化された構成パターンがあります。
それらを知っておくと、聴くときの楽しさが増すだけでなく、
自分で作曲する際のアイデアにもなりますよ。
パターン1:王道の「Aメロ → Bメロ → サビ」型
最もよく使われるパターンです。
しっとりと始まるAメロ、徐々に盛り上がるBメロ、そして感情を爆発させるサビ(Cメロ)。
まさに「起→承→転→結」の流れを感じられる構成です。
・イントロ → Aメロ → Bメロ → サビ → 間奏 → Aメロ → Bメロ → サビ → サビ(繰り返し)→ アウトロ
多くのヒット曲でもこのパターンが採用されており、
リスナーにとっても自然で聴きやすい流れになっています。
パターン2:サビ始まり型(キャッチー重視)
最近のJ-POPやアニメソング、SNS向けの楽曲などでは、
サビから始まる構成(いわゆる“サビ頭”)も増えています。
最初から強く印象を与えることで、リスナーの心を一気につかむ効果があります。
・サビ → Aメロ → Bメロ → サビ → 間奏 → サビ(繰り返し)→ アウトロ
短時間でインパクトを出したいときにぴったりな構成です。
パターン3:Bメロを省略したシンプル構成
曲によってはBメロを入れずに、Aメロ → サビという構成だけで展開することもあります。
テンポが速い曲や、短めの楽曲、シンプルでわかりやすい印象を与えたいときに使われます。
・イントロ → Aメロ → サビ → 間奏 → Aメロ → サビ → サビ → アウトロ
Bメロがない分、Aメロとサビにしっかり個性を持たせるのがポイントです。
パターン4:Dメロを加えて変化をつける構成
曲の後半で、新しい展開を加える「Dメロ」を取り入れることで、
ストーリー性や緩急を強く印象づけることができます。
・Aメロ → Bメロ → サビ → 間奏 → Aメロ → Bメロ → サビ → Dメロ → サビ → アウトロ
Dメロではテンポが変わったり、キーを転調させたりすることもあります。
このように、曲の構成にはいくつかの「型」があります。
もちろんすべてがこの通りというわけではありませんが、
基本的なパターンを理解しておくことで、曲作りの指針や、アレンジのヒントにもなります。
次は、こうした構成をベースにしながら、
リスナーを飽きさせない工夫について見ていきましょう。
なぜ曲構成が大事?-リスナーを飽きさせない仕組み–
「メロディやコードがよければ、構成はあまり気にしなくてもいいのでは?」
そう思う人もいるかもしれません。
たしかに、印象的なメロディは大きな武器になります。
ですが、どんなに良いメロディでも、構成が単調だとリスナーは途中で飽きてしまうことがあるんです。
曲構成は“感情の流れ”をつくる設計図
音楽は感情を動かす芸術です。
Aメロで世界観を静かに描き、Bメロで期待を高め、サビで一気に感情を開放する。
このように構成を意識することで、聴き手の感情に寄り添ったストーリー性のある曲作りができるようになります。
逆に、感情の流れが急すぎたり、平坦すぎたりすると、
「なんとなく退屈」「印象に残らない」と思われてしまうことも…。
曲構成は“飽きにくさ”にも直結する
人は同じメロディやコードが続くと、自然と聴き飽きてしまいます。
そこで、「Aメロ→Bメロ→サビ→間奏→Dメロ…」といったように構成を工夫することで、
曲に変化とメリハリが生まれ、最後まで聴き続けたくなる仕掛けが作れるのです。
Bメロや間奏、Dメロなどは「変化球」として、
リスナーの耳をリセットする役割も持っています。
初心者ほど“構成の型”を活かすべき
プロの作曲家でも、構成には一定の型やテンプレートを意識して曲を組み立てています。
特に初心者のうちは、自由に作るよりも一度“型”をしっかりなぞってみることで、
自然な流れや“聴き手の心地よさ”を体感できるようになります。
曲構成は、あなたの音楽をより伝わりやすく、
記憶に残るものにしてくれる大切な要素なんです。
次の章では、型にとらわれない自由な構成や、「Aメロ・Bメロが無い曲」など、
もっと幅広いアイデアについてもご紹介していきます。
Aメロ・Bメロが無い曲も?自由な構成の発想法
ここまで、Aメロ・Bメロ・サビといった定番の構成について紹介してきましたが、
実は、これらのブロックが無くても成立する曲もたくさんあります。
音楽に絶対のルールはありません。
構成はあくまで“表現の手段”であって、
自由にアレンジしたり、型を崩したりすることもできるんです。
Aメロ・Bメロを省略してサビだけで展開する曲
最近では、特にSNSでの再生を意識した楽曲などで、
最初からサビだけを繰り返すような短い構成も増えてきています。
こうした曲では、イントロを省略し、いきなり盛り上がるサビから始まることで、
最初の数秒で聴き手の心をつかむ工夫がされています。
・サビ → サビ変化形 → 間奏 → サビ(繰り返し)→ フェードアウト
このような構成は、短くてもインパクトを残せるのが魅力です。
パートを自由に追加する構成(DメロやEメロなど)
定番の構成にとらわれず、必要に応じてDメロ・Eメロなどの新しいパートを追加するのも自由です。
たとえば、Cメロ(サビ)の後に一度落ち着いたDメロを入れてから再び盛り上げることで、
物語の「クライマックス」のような構成に仕上げることができます。
実際の楽曲でも、Dメロでガラッと雰囲気が変わったり、
テンポやキーを大胆に変えることがあります。
この“意外性”が、リスナーに強く印象を残すこともあるんです。
インストやBGMこそ構成は自由!
歌のないインスト曲やBGMでは、さらに自由な構成が可能です。
「Aメロ・Bメロ」という言葉は使わなくても、
パートごとに雰囲気や展開を変えることで、場面の変化を演出できます。
たとえば、映像作品のBGMでは、1つの楽曲の中で「導入 → 急展開 → 落ち着き → エンディング」など、
場面の流れに合わせて自然に構成を変化させることがよくあります。
音楽の構成には「正解」があるわけではありません。
まずは基本のパターンを学び、そこからあなたなりの自由な展開を見つけていくのが、
創作の楽しさでもあります。
次は、「Cメロって何?」「Dメロって必要なの?」といった、
よくある疑問にお答えしていきますね。
よくある質問:Cメロって何?Dメロって必要?
「Aメロ・Bメロ」はよく耳にするけれど、
「Cメロ」「Dメロ」となると、少し専門的に感じるかもしれませんね。
でも、難しく考えなくても大丈夫。
ここでは、CメロやDメロがどんな役割を持っているのか、そして必ず必要なのか?という
よくある疑問にお答えします。
Cメロとは?=サビのこと
「Cメロ」という言葉は、多くの場合「サビ」のことを指します。
Aメロ・Bメロと展開してきた流れの中で、感情が一気に盛り上がるパート。
それがCメロ=サビです。
ただし、楽曲によっては「Cメロ」という言葉が“サビとは別の展開部分”を指す場合もあります。
たとえば、Aメロ→Bメロ→サビ(Cメロ)と進んだあと、
さらに全く雰囲気の違うパートが登場することがありますよね?
このような場合は、その新しい部分を「Cメロ」、そしてサビを「Dメロ」と呼ぶこともあります。
つまり、曲のブロックを順番に「Aメロ→Bメロ→Cメロ…」のように呼ぶので、
必ずしも、「Cメロ」部分がサビというわけではありません。
呼び方は曲の構成や制作者の考え方によって多少変わるということなんですね。
Dメロとは?=サビのあとに入れる“変化球”
Dメロは、主に曲の後半に登場する「展開パート」のこと。
それまでの流れを一度リセットし、新しい雰囲気や展開を加えることで、
サビの再登場をより強く印象づける効果があります。
たとえばDメロでは、
- テンポが変わる
- リズムが変わる
- キーが転調する
- メロディが大胆に変化する
といった演出が使われることが多いです。
Cメロ・Dメロは「必要」なの?
答えは、曲の目的や雰囲気によって変わります。
たとえば
- 短くてインパクト重視の曲 → Dメロは省略してもOK
- ストーリー性のある曲 → Dメロで物語に「転」を作ると効果的
- クライマックスで印象を強めたい → CメロとDメロのメリハリが有効
つまり、「必ず入れなければいけない」というものではありません。
ただし、曲に起伏やサプライズを与えたいときには、非常に便利なツールになります。
作曲に慣れてきたら、
CメロやDメロを“どこにどう配置すれば曲がより魅力的になるか”という視点で、
少しずつ使い方を研究してみるのもおすすめです。
次はまとめとして、これまでの構成のポイントを振り返りつつ、
曲づくりにどう活かしていけるかを整理していきましょう。
まとめ|構成を知れば、作曲はもっと自由で楽しくなる
曲づくりにおいて、Aメロ・Bメロ・サビといった構成は、
単なる順番ではなく、感情やストーリーを演出するための大切な仕組みです。
基本の型を学ぶことで、曲の聴き方も変わり、
自分でも「こんな曲を作ってみたいな」という気持ちが自然と湧いてくるはずです。
音楽に決まりきった正解はありません。
だからこそ、構成の基本を知ることは、あなたの“自由な音楽”を作るための第一歩になります。
もし「作曲って面白そう」「自分でも曲を作ってみたい!」と思ったら、
まずは気軽に読める無料メール講座『作曲7つの基本』から始めてみませんか?
▶︎ 無料で学べる!作曲7つの基本(メール講座)はこちら
初心者でもわかりやすく、基礎から丁寧にステップアップできる内容なので、
楽しみながら「自分だけの音楽」を形にする第一歩になりますよ(^◇^)ノ
→音楽制作の知識大全「音楽レシピ(作り方)の図書館」のもくじへ戻る