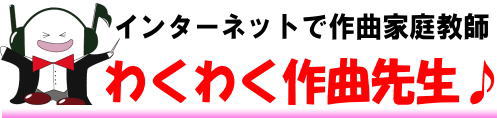今回は「転調」の実践編第3回です。
転調の理論についてはバックナンバーで解説しているので、
忘れた方は読み返してみましょう。
さて、今回は一時的転調のお話です。
前回まではドミナントモーションを使った転調を紹介しましたが、
ドミナントモーションは1回だけしか使えないとは限らないのです。
つまり2連続、3連続させるというテクニックもあります。
例を挙げましょう。
【Bメロのコード進行】
D – E – Cm7 – F#m7
【サビのコード進行】
C – Am – F – G
この場合、keyの違うBメロとサビをつなぐためにドミナントモーション「G7」を使いましたよね。
(D – E – Cm7 – F#m7) – G7 – (C – Am – F – G)
このG7へドミナントモーションするコードは何でしょう?
ドミナントモーションは完全4度進行なので、逆算するとD7ですよね。
これを取り入れるとこうなります。
(D – E – Cm7 – F#m7) – D7 – G7 – (C – Am – F – G)
同じくこのD7へドミナントモーションするコードは何でしょう?
A7ですね。
これを取り入れると
(D – E – Cm7 – F#m7) – A7 – D7 – G7 – (C – Am – F – G)
このように連続することでカッコイイ響きを作り出すことができます。
ではどこまでやればいいかというと、特に決まりはありません。
一つの考え方としては、Bメロの最後「F#m7」からドミナントモーションが始まるようにする方法がスムーズでしょう。
(D – E – Cm7 – F#m7) – B7 – E7 – A7 – D7 – G7 – (C – Am – F – G)
ではまた次回、おたのしみに~ (^o^)/~~
次の講座_第48回「転調のやり方4」を読む
前回の講座_第46回「転調のやり方2」を読む
「作曲編曲のやり方87の法則 」もくじへ戻る
初心者からのオンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る