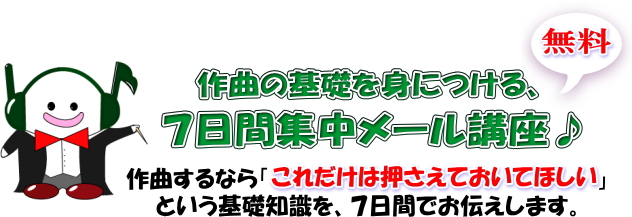■わくわく作曲先生HOME > DTM、作曲、レコーディングの豆知識 > インターバル(音程)の重要性インターバル(音程)の重要性難易度3★★★☆☆___________ 今回は「インターバル(音程)の重要性」について書いてみましょう。 「インターバル(音程)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 音楽理論の専門書を見てみると必ず載っている、 「長3度」「完全4度」「M7」「aug5」などの用語です。 このインターバルの重要性はあまり知られていないと思いますが、 実はとても重要です。 「インターバルを知らずして、本格的な作曲は出来ない」と言っても 過言ではないでしょう。 ギター片手にコードを弾きながら、メロディを口ずさんで作っていくのならば、 ある程度のレベルまでなら作曲できます。 コードの押さえ方さえ知っていれば、形になりますからね。 ですが複雑なコードの作り方や、転調、独特のスケールなどは 使えないはずです。 たとえばコードの仕組みを考えてみましょう。 「C」というコードは「ド、ミ、ソ」から成ることは良く知られていますが、 なぜ「ド、ミ、ソ」なのでしょうか? そして「D#」や「Ab」などの構成音が、すぐに思い浮かぶでしょうか? コードの構成もインターバルで決まっています。 「C」のようなコードは「メジャートライアド」と言って、 「ルート、長3度、完全5度」の組み合わせからなるコードです。 「D#」や「Ab」などでも全て、「ルート、長3度、完全5度」の組み合わせです。 このように「ルート、長3度、完全5度」の組み合わせにすると、 「メジャートライアド」の明るい響きが得られます。 つまり、「音」が重要なのではなく 「インターバル(音と音の間隔)」が重要なのです。 2つ以上の音が共鳴することで、さまざまな響きを作り出します。 カラオケなどでよく「キーを変える」と言いますが、 なぜ「キー」を変えても、曲の構造は変わらないのでしょうか? 答えは、「音が変わっても、インターバルは変わっていない」からです。 コード進行も、「何度上がるか(下がるか)」によって、 曲の流れが変わってきます。 同様に、転調も「何度のコードをどこに持ってくるか」と考えます。 インターバルが必要な場面はまだまだありますが、 重要性は分かって頂けたのではないでしょうか? 本格的な作曲をやるならば、 インターバルだけはマスターしておきましょう。
 →わくわく作曲先生「作曲87の法則」へ戻る | |||
|
よくある質問|作曲ノウハウ|コミュニティ Waimプロデュース 4th-signal MusicのTOPページ 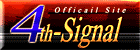 Copyright(C) 2003-2014 4th-signal Music All rights reserved このサイト内の音楽、画像、文章の無断使用はご遠慮下さい。 |