オーディオデータをくっつける際に気を付けること
わくわく作曲先生♪トップページ > DTM、作曲、レコーディングの豆知識 > オーディオデータをくっつける際に気を付けること
今回は「オーディオデータをくっつける際に気を付けること」について書いてみましょう。
オーディオデータ(波形データ)は、切り貼りできるので、
音が鳴るタイミングを修正したり、
順番を変えることで、新たなフレーズを作ったりすることができます。
ただ、2つのオーディオデータをくっつける際、
つなぎ目でノイズが乗ってしまう場合があります。
これを防ぐには、大きく分けて2つの方法があります。
まず1つは、クロスフェードという処理です。
クロスフェードとは、オーディオデータの境目で
「フェードアウト+フェードイン」を、
ごく短い時間におこなうような処理です。
たとえば、前後2つのオーディオデータをつなげる場合、
前のオーディオデータはフェードアウト(スムーズに音が消えて行く状態)で終わらせます。
これにより、音が「ブツッ」と切れることを防ぎます。
後ろのオーディオデータは、フェードイン(スムーズに音が聞こえ始める状態)で始めます。
これにより、急に音が鳴り始めることを防ぎます。
このフェードアウトとフェードインを
オーディオデータのつなぎ目で、同時におこなうことにより、
ノイズを抑えることができます。
この処理が「クロスフェード」です。
もう一つは「ゼロクロスポイント」を意識することです。
オーディオデータを拡大して見ると、
「波の形」であることが分かります。
音自体が波ですからね。
そのため、オーディオデータは波形データとも呼ばれます。
波は、プラス方向(山の形)とマイナス方向(谷の形)に分けることができます。
そして、プラス方向とマイナス方向が切り替わる境目を、
「ゼロクロスポイント」と言います。
名前の意味を考えると、想像しやすいのではないでしょうか。
先ほど書いたように、ノイズが乗る理由は、
音が鳴っている途中で波形が切れたり、
逆に、波形の途中から急に音が鳴り始めるためです。
つまり、オーディオデータを切り取る時には、
波形の途中ではなく、「ゼロクロスポイント」で音を切ると、
ノイズが乗らなくなります。
DTMソフトによっては、「ゼロクロスポイント」を自動で検出してくれる機能もあるので、
活用すると良いですね。
以上のことを意識して、オーディオデータ編集を楽しんでくださいね(^◇^)ノ
→「DTM、作曲、レコーディングの豆知識」のもくじへ戻る
→オンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る
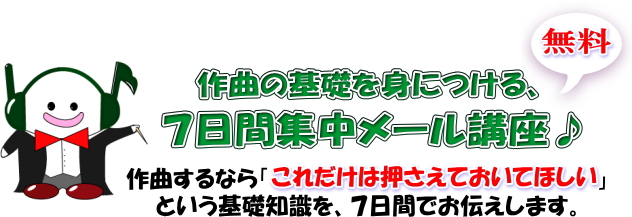 その後は、まぐまぐ時代にエンターテイメント部門1位を獲得した メルマガ「秘密の音楽法♪」の最新版を、毎週お届けします。 購読は無料です。 今すぐご登録ください♪ ※メールアドレスが間違っていると届かないので、 正確にご記入ください。 |

